カルナバイオ Research Memo(7):2017年12月期は研究開発費の増加などにより営業損失がやや拡大
1. 2017年12月期の業績概要
2017年12月期の連結業績は、売上高で前期比19.0%減の657百万円、営業損失で699百万円(前期は423百万円の損失)、経常損失で711百万円(同440百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純損失で737百万円(同289百万円の損失)となった。
売上高は前期に創薬事業で計上したCDC7キナーゼ阻害薬に関するライセンス契約一時金収入98百万円がなくなったことに加えて、創薬支援事業でも国内の売上減少が響いて減収となり、前期比で154百万円の減収となった。費用面では、BTK阻害剤2品目の前臨床試験開始に向けた費用を中心に研究開発費が前期比157百万円増加し、この結果、営業損失は前期比で275百万円拡大した。また、前期は特別利益として投資有価証券売却益177百万円を計上したこともあり、親会社株主に帰属する当期純損失については前期比447百万円拡大している。
2. 事業セグメント別動向
(1) 創薬事業
創薬事業では、期初計画で2016年にシエラに導出したCDC7キナーゼ阻害薬※(シエラの開発番号:SRA141)の臨床試験開始に伴うマイルストーン収入(4百万ドル)を予定していたが、臨床試験の開始が2018年にずれ込んだため売上計上はなかった。一方、営業損失は研究開発費の増加により前期の616百万円から841百万円に拡大した。
※ CDC7キナーゼ阻害薬のメカニズムは、細胞分裂する際に重要なDNA複製等の染色体サイクルにおいて、その制御に深く関与しているCDC7キナーゼを阻害することで、がん細胞におけるゲノムの不安定化を引き起こし、がん細胞を死滅させるというもの。正常細胞については影響を受けないため、副作用のリスクも低いと見られている。シエラでは、DDR(DNA damage response:DND修復機構)に関与するキナーゼ阻害薬の開発にターゲットを絞って開発を進めている。
CDC7キナーゼ阻害薬は多くのがん腫で治療効果があると見られるが、シエラが本年2月27日に公表したSRA141の抗腫瘍活性の結果の内容によると、ラットを用いた血液がん(MV4-11)および大腸がん(colo-205)の担癌モデルにおいて、SRA141はその腫瘍増殖を強力に阻害し、血液がんのモデルでは一部のラットが完治し、さらに大腸がんのモデルでも半数以上で腫瘍の退縮が観察されたと報告された。この結果に基づき、シエラは2018年下半期のIND申請を予定しており、大腸がん患者を対象としたフェーズ1/2試験に進めていく予定である。大腸がんをフェーズ1/2の疾患領域とした背景には、シエラによる先行開発品(武田薬品工業<4502>:第2相臨床試験中、イーライリリー:第1相臨床試験中)の開発の状況を分析し、戦略的に開発方針を決定したものと思われ、シエラはSRA141の開発を一時スローダウンしたが、このような判断を行なう上での戦略とも考えられる。シエラとの契約では、CDC7キナーゼ阻害薬プログラムの進捗に伴うマイルストーン収入総額が270百万ドルとなっており、上市後の売上高に対するロイヤリティ率は1ケタ台後半のパーセンテージと見られる。
なお、2017年12月期のトピックスとしては、第1四半期にEpiBiomeとの共同研究契約を締結している。第2四半期には日本のがん免疫療法研究の第1人者である慶應義塾大学医学部の河上裕(かわかみゆたか)教授と新たながん免疫療法の確立を目的とした共同研究契約を締結しており、がん免疫療法が注目されるなか、新しい免疫チェックポイントモジュレーター薬の開発を目指す。
(2) 創薬支援事業
創薬支援事業の売上高は前期比7.7%減の657百万円、営業利益は同25.6%減の142百万円となった。売上高の内訳は、国内向けが前期比15.8%減の352百万円、北米向けが同5.4%増の210百万円、欧州向けが同9.2%減の65百万円、その他地域向けが同31.7%増の29百万円となった。国内向けについては、主力顧客である小野薬品工業向けの売上高が、研究開発費抑制の影響もあって前期の194百万円から144百万円に減少したことが減収要因となったが、他社向けの売上は堅調に推移した。また、北米向けは主にセルベースアッセイサービスの売上高が増加し、前期比で売上が伸びている。欧州向けについてはキナーゼタンパク質やプロファイリングサービスが好調だったものの、12月に計上予定だった案件が期ズレしたことにより減収となった。この影響がなければ欧州向けは横ばい水準であった。その他地域については、主に中国、韓国向けが伸長した。規模的にはまだ小さいものの、中国でもキナーゼ阻害薬の創薬開発が活発化したことがうかがえる。
なお、2017年12月期は脂質(Lipid)キナーゼであるDGK(ジアシルグリセロールキナーゼ、活性型全10種類を販売しているのは世界でもカルナバイオサイエンス<4572>のみ)に関する大型アッセイキット(約1億円/件)の受注獲得を目指していたが、期中の受注獲得には至らなかった。ここ1~2年でメガファーマや有力バイオベンチャーの経営戦略が変化しているのが要因と見られる。具体的には、創薬にかかる開発費用が増加する一方で、成果が上がりにくくなっているため、基礎研究からスタートするよりも有望なパイプラインを持つバイオベンチャーをM&Aでグループ内に取り込む戦略に変わってきている。こうした経営戦略の変化によって、各企業とも研究投資の判断が慎重になっており、その影響が少なからずあったと見られる。
ただ、DGKは低分子によるがん免疫療法の分野において注目度が高いことに変わりない。がん細胞を攻撃するキラーT細胞の働きに関与していることが明らかとなっているためだ。具体的には、DGKα及びDGKζと呼ばれる2種類のキナーゼが、キラーT細胞を眠らせる信号を伝達する役割を果たしている。このため、DGKαとDGKζの働きを阻害する薬剤ができれば、キラーT細胞の働きを活発化させ、がん細胞への攻撃力を回復させる効果が期待できる。オプジーボなどのチェックポイント阻害剤を使った治療では、メラノーマなどのがん患者に対して3割程度の患者にしか治療効果が現れないが、これは全身の免疫力が低下している患者、もしくは免疫力があってもキラーT細胞が十分活動していない患者だと推測されている。DGKα及びDGKζを標的とする治療候補化合物が開発されれば、がん免疫チェックポイント阻害剤との併用により治療効果も一段と高まることが予想される。
DGKは基質が脂(Lipid)であることから水に溶けないため、アッセイ系の構築や取扱いが非常に難しく、単にDGKタンパク質を購入してもアッセイ系を構築するのに相当の時間がかかる可能性が高い。このため現在、同社では既に開発しているアッセイキットの販売に取り組んでいる。現在は、顧客にて小スケールでの評価が進行中となっており、2018年中の大型受注契約獲得を目指している。
その他、2017年12月期のトピックスとしては、共同研究先である米 EpiBiome, Inc.が持つマイクロバイオーム(細菌叢)のプロファイリングサービスを第3四半期から開始したほか、米MITから独占的に技術ライセンスを受けているベンチャー企業であるAssayQuant Technologies, Inc.のキナーゼアッセイキットの国内での販売を第4四半期から開始した。また、知財の確保ではCDC7キナーゼ阻害薬に関して日本、オーストラリア、メキシコで特許登録を行ったほか、TNIK阻害薬に関して日本、米国、中国で、BTK阻害薬に関して日本、米国、韓国、オーストラリアでそれぞれ特許登録を行った。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
<MH>
杏、連絡先知らない芸人がパリの自宅を訪れ…子どもたちの反応明かす
“役満ボディー”岡田紗佳、ビキニ&ヘルシー下着ショット 最新写真集の8月発売を報告
石原良純「ゴルフ好きの人の中では触れない話題」全米OP2位渋野日向子の“復活”に感慨
落語家の笑福亭智六さん死去、45歳 闘病しながら高座 「動物園」「相撲場風景」を十八番
大谷翔平サインカードに高値! ルー・ゲーリッグ・デーにMLBがチャリティーオークション
中丸雄一と結婚の元日テレアナが近影公開 新ヘアスタイル披露
ベッドで頭をぶつけたワンちゃん イテッ!と言わんばかりの表情にクスッ
「とんでもねぇ美人だ!!」GENKING.黒ビキニ姿が話題 性適合手術から7年を回想
元日テレ笹崎里菜「HPができました」ふんわりニット写真で報告 中丸雄一の妻
山之内すず、神戸から上京して運動不足に “神戸ならでは”の恩恵があった
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
浜崎あゆみ、子供の写真公開に疑いの声止まず「よそのお宅の子供?」
大谷翔平被弾投手が悪態ついて退場処分!次打者フリーマンと対戦中に判定巡り塁審と口論
YouTuberジュキヤの動画企画が大炎上「普通に痴漢」「気持ち悪すぎ」
千原せいじのシエラレオネ巡る発言 NPO代表理事が公式謝罪忠告「最悪、国家間の問題に発展」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
大谷翔平10試合ぶり14号 シティフィールド初アーチ、26球場目は自らの日本人記録更新
大谷に被弾→次打者判定で審判と口論→退場→「チーム、自分も最悪」→戦力外
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
大原櫻子、ガーシー暴露後初のSNS投稿に賛否の声「イメージ最悪になった」
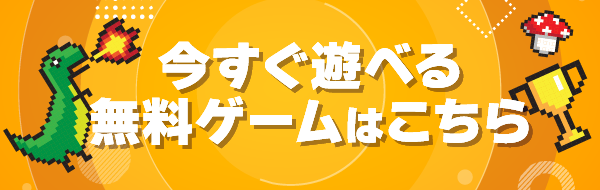
杏、連絡先知らない芸人がパリの自宅を訪れ…子どもたちの反応明かす
“役満ボディー”岡田紗佳、ビキニ&ヘルシー下着ショット 最新写真集の8月発売を報告
石原良純「ゴルフ好きの人の中では触れない話題」全米OP2位渋野日向子の“復活”に感慨
落語家の笑福亭智六さん死去、45歳 闘病しながら高座 「動物園」「相撲場風景」を十八番
大谷翔平サインカードに高値! ルー・ゲーリッグ・デーにMLBがチャリティーオークション
中丸雄一と結婚の元日テレアナが近影公開 新ヘアスタイル披露
ベッドで頭をぶつけたワンちゃん イテッ!と言わんばかりの表情にクスッ
「とんでもねぇ美人だ!!」GENKING.黒ビキニ姿が話題 性適合手術から7年を回想
元日テレ笹崎里菜「HPができました」ふんわりニット写真で報告 中丸雄一の妻
山之内すず、神戸から上京して運動不足に “神戸ならでは”の恩恵があった
